土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
「その日は突然やってきた」
あれは、モスクワに到着して1か月くらいが経った頃だったろうか。季節は初冬、もうすでに何度か雪が降り、街中でも所々積もっていた。その日の早朝、めずらしく、いや多分初めて父が、私と兄が寝ていた子供部屋に入ってきて、短くこう言ってすぐに出て行った。
「朝飯の後、すぐ出かけるから余所行きの服を着とけ。」
当時私は自分で着替えができなかった。「どうしよう・・・」と、まだ覚め切らない頭でぼんやりと考えていると、やがて母が真新しい下着とお坊ちゃん風の余所行き着を一式持ってきた。白いワイシャツ、ベージュのセーター、兄とおそろいの灰色のズボン、ワンポイント刺繍が付いた靴下、そして黒の革靴。母は黙ったまま、パジャマを脱がせて、その余所行き着一式に着替えさせてくれた。
着替えの途中、「日曜日やないのに、何処行くん?」、という私の問いに、母は答えずじまいだった。
私はお出掛けが好きだった。めったになかったお出掛けが。その時に着せてもらえる余所行きの服も大好きだった。着るだけで誇らしい気分になって、仕上げに、横側に赤い鳥の羽が付いたチロル帽を頭にポンとのせてもらう。それだけでワクワクは最高潮になったものだ。
着替えが終わると私は、母に抱きかかえられて台所兼食堂に行った。母があの時、私を抱いて連れて行ってくれたのは、床を這いずることしかできなかった私が余所行き着を汚さないように、とのことだったのだろうが、考えてみれば、私が母の腕に抱かれたのは、たぶん、あれが最後だったような気がする。
台所に入ると、新聞を読みながら先に食べ始めていた父が母に言った。
「車の中で、またトイレだの気分悪いだの言われたら困るし、あんまりようけ食べさすなよ。」
ジャム付きのパン一枚を頬張り、紅茶を飲み終えた私は、歯磨きの代わりに洗面器でうがいをさせてもらい、すぐに厚手のコートを着せられ、今度は父に抱きかかえられ玄関を出た。モスクワの家は12階建てのアパートメント(今の日本で言えばマンション)で、エレベータで降りていく途中、私は父に尋ねた。
「今日は何処行くん?」
「お前の足を歩けるようにしてくれるセンセとこ行くんや、すぐ終わるから・・・。」
と父はまっすぐ前を向いたまま、面倒くさそうに早口で答えた。
建物の出入り口には、もう薄黄色のボディの横にチェッカー模様が入ったタクシーが止まっていた。排気ガスというよりは生のガソリンの濃い匂いを、冷気で硬くなった辺りの空気に撒き散らしながら。
家族4人、両親と兄そして私が乗り込むと、車はすぐさま発進した。行き先は既に予め運転手に伝えられていたようだった。サーカスで滑稽な芸を披露する熊のように大きな、大きな体の運転手は、綿入れのようなカーキ色の上着にベレー帽をかぶり、子供の眼にも陽気そうなおじさんだった。
車は30分くらいで市内を抜け、雪原と真っ黒な森が所々に現れる、どこまでも真っすぐな道をひたすら走っていった。余所行き着に着替えさせてもらっていた時のあのワクワク感はいつの間にか消え失せていて、私は黙りコクって車窓の外を見ていた。
空はどんより暗灰色の雲が垂れ込めていて、車が進んで行く方角では、遥か遠くで空と地面の境目がボヤけていた。
そのドライブは3時間続いた。
赤國幼年記3につづく
◆プロフィール
古本聡(こもとさとし)
1957年生まれ。
脳性麻痺による四肢障害。車いすユーザー。 旧ソ連で約10年間生活。内幼少期5年間を現地の障害児収容施設で過ごす。
早稲田大学商学部卒。
18~24歳の間、障害者運動に加わり、障害者自立生活のサポート役としてボランティア、 介助者の勧誘・コーディネートを行う。大学卒業後、翻訳会社を設立、2019年まで運営。
2016年より介護従事者向け講座、学習会・研修会等の講師、コラム執筆を主に担当。















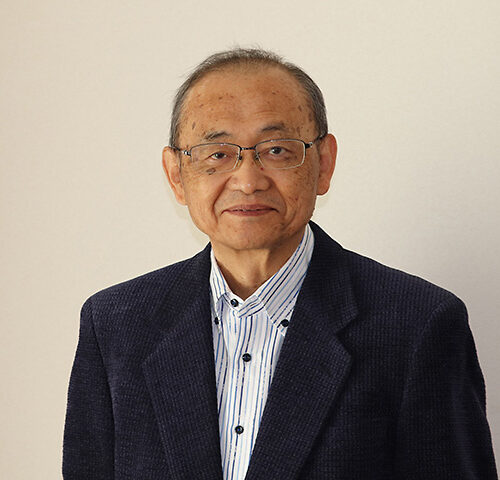




-1.png)




















