土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
私が小学校に入学したのは1963年。その頃には登校拒否とか不登校という概念は全くなかった。あるのは障がいの重い子に対する通学拒否、「ここはあなたの来れる場所ではない」という学校側からの就学免除という拒絶権だった。私は就学児検診を受け、「知能は普通」ということでそれは認められた。しかし実際に入学したのはその1年後。その間にまず手術が重要、と就学猶予となった。兄がいたので兄は小学校に行っているし、妹は幼稚園に通っていた。だから小学校に行くのはその年齢になれば当たり前だと思っていたにもかかわらず、「障害があるという事は人と違う扱いを受ける」という最初の呪縛だった。
まず7歳で、学校ではなく病院に入院して生まれて初めての手術をされた。曲がった大腿骨を真っ直ぐにするという手術で、学校に行く前にしておいた方がいいと医者に勧められたのだった。別に骨が曲がっていても本人にとってそれほど不都合はないにも関わらず当時は医者の権威が絶大で、それに抗うことは到底出来ないと、母も私も思わされていた。その後13歳で「もう二度と手術はしない。西洋医学による整形外科は自分の体には必要がない。」と決断するまでは、8回くらい手術された。
一口に手術というが本来それは命を助けるためのものではないだろうか。私のように、曲がった骨を真っ直ぐにしようという医療の側の好奇心向学心によってメスで身体を切り刻まれる。それが正当なこととは、どんどん思えなくなっていった。なぜなら、手術の痛みは絶望的で、骨を真っ直ぐにすることがそれを超えるほどの価値を持つとは、とても思えなかったのだ。その上、医師たちは「私の人生のために良いことをしてあげたのだ」と言い放った。
そうした医療との関わりがまずあって、教育もまた「骨の弱い子であっても就学してきて良いよ」と小学校の校長が言った。障がいのない子たちには学校は当然のように行ける場所、行く場所でありながら障がいのある私には来ていいよとの許可制なのは、なぜなのか?それは、差別だと直感し、愕然とした。
と言っても私もたった7歳だったから、差別であるという直感はあったけれど、それを「愕然」という言葉に置き換えてはいなかったが。多分その違和感は校長の言葉に「ありがとうございます。」というように卑屈に頭を下げる母の姿を見て感じたのだろう。その後母は「校長先生が良い人でよかった。」と言っていたし、周りの大人たちも口々にそう言った。
病院で痛い注射をされても骨が強くなっているかもわからない。“治療”という名目で、骨をわざと切られるような手術を受けても「ありがとうございます。」と頭を下げていた母。その母に対する苛立ち。「私以外の子どもたちの親は何も言わないのに、また母だけが言っている」ということで、私は心の底で憤慨していたのだった。
もし私が障害がなかったら私も学校の有り様にうんざりしていたから、不登校をしただろうか。いやそうは全く思えない。障害がなければ過酷な点数市場主義の競争に巻き込まれていたにちがいない。「できない子」を心の中で見下し、「できる子」にやっかみをもちながら、通い続けていたことだろう。
競争させられて、「勝ち組にいった方がいい」という思いは、小さい頃から押し付けられ、刷り込まれていく。小学校4年までの地域の学校では、それでも競争より助け合いの方が価値があった。私をおぶって送り迎えしてくれる母を見ていたから、小学校4年くらいになると、体格のいい同級生たちが私のことをおんぶしたがった。また私の同級生に父子家庭の子がいた。その子は、とても清潔ではない格好でいたから、私はその子が嫌いだった。にも関わらず、その子は私の母が好きで、よく私たちに近づいてきた。母は、「お互い様だよ。」と言いながら、その子の鼻をよく拭いてあげていた。
小学校5年から私は、手術のために養護学校に転校することになった。先述の、痛いだけの手術をされた病院施設(療育園)と養護学校は廊下一本で繋がっていたのだった。養護学校教育は、全体をもし10とすれば、私にとって、良いところは1/10もなかったろう。まず、教員たちのやる気のなさは半端なかった。私を受け持った教員たちが特にそうだったのかもしれない。ベッドサイドスクールで教えに来たはずの教員たち。しかし、その実態は、手芸をしたり、株式情報を聞いたりなど、あるいは、数ヶ月に一度しか顔を見せなかったりなど、やりたい放題だった。私の質問には、「お前たちに教えても無駄なんだ」と言った教員もいて、私の学びたいという意欲もどんどん消失していった。
私の体の具合が良い時は、廊下を渡って養護学校にも通った。その時のクラスは、養護学校の寮生と園から通う子の5、6人のミックスだった。しかし学んだことは、「差別し合ってもいい」という恐ろしいことだけだった気がする。私の隣の席の子は居眠りばかりしていたので、「こんな子とおしゃべりしていたら勉強ができなくなるばかりだから、こういう子と遊んではいけません。」と教えられた。その後10年後くらいに、その子に会った時、なぜあんなに居眠りをしていたのかを聞いてみた。すると、当時彼女は緊張留めを朝食の後に数錠処方されていたということだった。あの居眠りの理由がその話ですっかり解けた。教員はその事実を知らなかったのだろうか。とにかく私は、1分でも早くこの場所から出なければまともな生活ができなくなると、どんどん焦っていった。
養護学校に入ったのは、手術をしてもベッドサイドスクールがあるので、進級ができると聞いていたからだった。しかし、ここで進級してもまともな授業がほとんどないわけだから、一体どうなるのだろう、と不安だった頃にさらに脊髄の手術を勧められた。
当時、脊髄の手術は実験でしかなく、明らかに危険だった。その手術が失敗して、寝たきりになった友達もいた。目の前に彼を見ながらその手術を受けるよう勧められて、恐怖が回った。私は医者の傲慢さに、ここにいたら殺されるとさえ感じたのだった。養護学校の教員たちの中には1人2人、私が「地域の学校に帰りたい」と言うと、「いやいや、ここにいてここから初めての大学進学者になれるよう頑張りなさい」という人もいた。しかしほとんどの教員は、我関せず、という感じだったから養護学校からの脱出にはそれほどの葛藤はなかった。
そしていよいよ西洋医学と決裂し、地域の学校に戻るという準備を始めた。両親を味方にして、療育園の園長にヒエラルキーを超えた交渉をした。ところが、そのすぐ後にまた骨折し、半年近く退院が伸びてしまった。今思い出すと、あの施設の中にいた2年半。一番骨折したし、勉強することもそれまでの中で最も面白くなかった。大人との関係も、母にだけ文句を言い続けていれば良かった時期と違い、四面楚歌、四方八方に敵ありという気分で生きていた。医療も教育も私を守ってくれはしないのだという辛い確信の下、退院となった。
◆プロフィール
安積 遊歩(あさか ゆうほ)
1956年、福島県福島市 生まれ
骨が弱いという特徴を持って生まれた。22歳の時に、親元から自立。アメリカのバークレー自立生活センターで研修後、ピアカウンセリングを日本に紹介する活動を開始。障害者の自立生活運動をはじめ、現在も様々な分野で当事者として発信を行なっている。
著書には、『癒しのセクシー・トリップーわたしは車イスの私が好き!』(太郎次郎社)、『車イスからの宣戦布告ー私がしあわせであるために私は政治的になる』(太郎次郎社)、『共生する身体ーセクシュアリティを肯定すること』(東京大学出版会)、『いのちに贈る超自立論ーすべてのからだは百点満点』(太郎次郎エディタタス)、『多様性のレッスン』(ミツイパブリッシング)、『自分がきらいなあなたへ』(ミツイパブリッシング)等がある。
2019年7月にはNHKハートネットTVに娘である安積宇宙とともに出演。好評で再放送もされた。










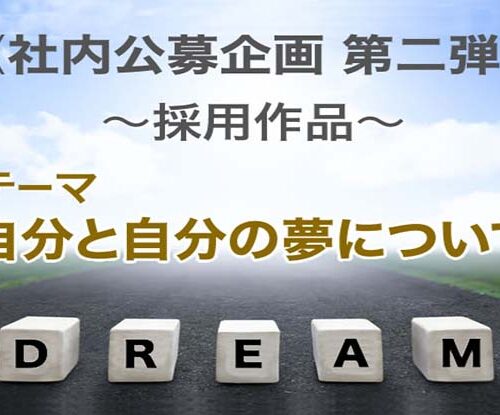
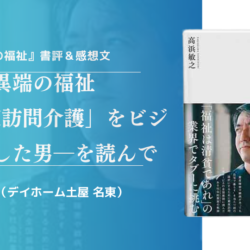





-1.png)















