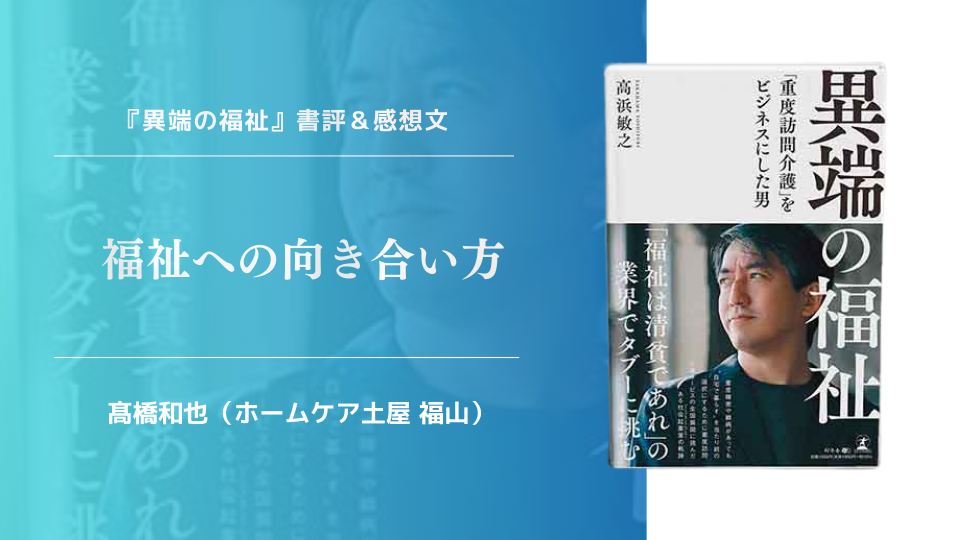
福祉への向き合い方 / 髙橋和也(ホームケア土屋 福山)
自分のルーツは広島県東部である。尾道で生まれ育ち、就学就職も地元を選んでいる。単にこの地域が好きであった、また都市部に憧れなどもなかったこともある。いくつか選択肢が常にあった中で選んだ結果ではあるが、昔、思い描いていた将来像からは違う気がする。
主に備後地域を中心に働いてきて紆余曲折あり、現在は井原に本社を置く会社に勤めたのも何かの縁である。地域の書店で綺麗に並べられた書籍の山を見た。
「異端の福祉」、理想の体現、傾聴、他者との同期。
介護福祉業界は人手が足りていない、本当に必要なところに必要な人員やサービスが提供されていないといったイメージがあった。職員側も給与面、資格などでなかなか就職先や転職の選択肢に入りづらい。
特に障害者福祉の成り立ちを考えると、家族の地域社会との関り、家族を取り巻く環境への制度の問題、選択肢の限られる生活環境、施設生活を余儀なくされ、自分らしい生活が送れない、閉鎖的な環境で個については配慮がなされていない点もクライアントからも聞く話だった。
実情を知ってもなかなか当事者・関係者にならないと、社会・制度を変えようという行動には移しづらい。時間も労力もかかるし、ゼロからのスタートで前例もない。何より強い力、意思やエネルギーがいる。
「小さな声」(P26)。株式会社土屋でも重要なワードである。本著によれば韓国の映画監督イ・チャンドン氏の言葉からくる。受け取り方は様々あるが、社会の中では埋もれている少数派の声であり、ただ1人が抱えている問題でもある。
大なり小なり個々に悩みや問題はある。障害をお持ちの方は望んでなっていない状況、ハンディを負った状況から社会生活をしなければならない。在宅介護を望もうが受け皿がない、人員が足りない、安定できない生活がどれほど不安であろうか。
自分も様々な縁があり業界に関わる事になるが、当時の話の中で「重い障害のある人は家族が在宅で世話をするか、施設に入るしか選択肢がありませんでした」(P36)。
重度の障害があれば施設で専門職しか対応も難しく、1:1で対応も難しく、施設でも生活リズムが相手任せにしかできない。プライバシーも自身の時間を取ることも難しく、外部との関りも薄くなったであろう。在宅であれば家族にも重い負担となってしまう。
当時の制度では重度の障害=守られる対象ではなく、世間とは隔絶されている。その状況下での新たな選択が、ボランティアの助けでの自立生活だ。重度の障害と一括りで言っても、個人の性格などの気質によってはやり方も違い、在宅は施設とはまた違う。在宅介護の原型が生まれた状況を考えると当然だと思う。
生きることは他人との対話であり、双方向のコミュニケーションである。社会で生きる以上、一方だけでは成り立たない。よりはっきりした世界だ。今ほどインターネットが普及していない時代では前例が少ない難病や障害を持っていても情報が収集できず頼れる機関、事業所、制度がわからなくて当然だ。
「小さな声」(P45)。ここでの対象は障害者である。健常者からはどうしても弱い存在、守るべき存在とされる。当事者に決定権がなく選択肢もない。障害がある事が「問題」なのだろうか。
「障害を生んでいるのは社会である」(P47)。世の中の多くは多数派に都合のいいようになっている。田舎よりも都会が発展しているように、弱者よりも強者に合わせてしまっている。平等な社会ではない。
「誰もが排除されないユニバーサル・デザイン」(P47)。実現に向けた大きな動きこそ、障害者自立生活運動であった。
特に少数の意見は社会に届きづらく把握しづらい。当事者たちにとっては自分たちの生活のため、また同じ境遇でやむを得なく現状に耐える者たちのためにも変えなければならなかったのだろう。1人の人権・尊厳を守るために。
介助する側に都合のいい施設・仕組みでは、される側は我慢するしかないだろう。閉鎖的で、する側が強い状況は想像を超える不自由であっただろう。長年の取り組み、運動活動で少しずつ改善されてはいった現在。変わっても変わりづらい事はある。
障害者に対する差別や、サービス・制度に関する受ける側に届きづらい環境がそうだ。介護職、看護職などは優しいイメージがある。警察官は正義感に溢れ法を犯さない。そうであってほしいが実際、介護現場で虐待や警察の不祥事もゼロではない。
個人の間違った考えや、甘え、驕りによっては障害者に対する偏見も時代が経ってもある。それにより行動や本人の意思を尊重されないサービスも大なり小なり存在する。制度があっても知らないまま、頼れないまま家族で支える、施設の空きもなく家族に負担を強いてしまい、本人も気に病むなどの問題もある。
重度障害者の過渡期としてボランティアの協力、地方を含めた自立生活者の認知・増大、生活を支えていたボランティアから有償労働へのシフト(P82)、登録ヘルパー制度の変革、世間との壁を少しずつ取り払っていった。
当事者や支援者の希望に沿わない形で進むことも数多くありながらで、順風満帆とはいえなかった。著者自身が精神・肉体も酷使し、体を壊しながらも巡り巡っての道を歩んでいく姿には驚愕する。弱い境遇の気持ちも寄り添え、更なる高い理想に立ち向かう姿を見た。
「神様、私にお与えください。自分に変えられないものを受け入れる落ち着きと、変えられるものを変えていく勇気を。そして、二つのものを見分ける賢さを。」(P94)。ここから何かが変えられそうな予兆がした気がした。
介護業界の経験、明確な意思に触れていた影響もあったとも思える。ご家族の様々な出来事を通しての新たな意欲と目標を手に立ち上がっていく原点回帰。
重度訪問介護の問題であるサポートできる事業所、人員または前例がない事での市など行政の対応、闘いはこれからだ。
前例がなければつくればいい。そういったメッセージが伝わってくる。すべての重度障害者が重度訪問サービスを受けられる世の中への挑戦が命題である。なぜすべての重度障害者に行き届かないのか。大きく5つの要因(P115)が挙げられる。
1.自宅で暮らせると思っていない
2.制度を知らない
3.自治体の財政負担が大きい
4.自治体ごとの熱意の差
5.事業者・人材不足
住んでいる自治体にも影響され、活用するにも安定な生活が送れるまで事業者・人員を待つのではすべての重度障害者には行き届かない。足りなければつくる、教育が必要であれば何とかする。人材不足の業界に新たなモデルが生まれていった。
周囲にも支えられつつ事業は動き出していった。施設と違い、クライアント宅での支援は人と人の対話には良い環境で自分らしい生き方のひとつの選択肢になった。
「福祉は清貧であれ」(P157)。大きく2つの目的に向けて会社は走り出す。
「介護難民ゼロ」、「福祉を夢のある仕事に」
福祉の起源・根幹にあるのは究極、無償の愛に近しいものがある。強制されるものではないので善意で、または身内だから愛情でもともと成り立ってきた。
聖人君子ばかりの世の中ではない。現実は見合った報酬がないと生活の維持や希望が見い出せない。重度訪問介護の特性として、施設よりも介助者一人の身体的な負担が少ない点から幅広い年代の人材が確保しやすく、個人1人に向き合いやすい。
自分も転職から業界にいるが、個人での信頼関係を築けるのもメリットだろう。社会に貢献でき、見合った報酬を得て喜んでもらえる活力が湧いてきた。社内での教育のシステムも大いに安心できた。未経験で介護歴がなくとも他に例を見ない特殊な介護(医療的ケア)で強みも十分であった。
今や全国各地に事業所を構え、実現したと言っても過言ではない状況でも夢はまだ終わらない。離島、山間部、過疎地域、言えば限りはないが「小さな声」は今もどこかに存在する。やるべき事、目標、価値。著者自らもまた受け継いだリレー(P245)の1走者だ。バトンを受け継ぐ者たちの存在。
社会を巻き込み、全ての人が分け隔てなく幸せに過ごせる。理想に向けてまだまだ道半ばであるのだろうが、競争社会で生きてきたが他者を害さず、ここまで個の幸福に寄り添える仕事はないと思う。
不遇に負けず喘いできた先駆者、活動。当時を思うと今、目の前にある仕事を誇りに感じる。自分も忘れかけていた夢に向けて動き出したくなった。









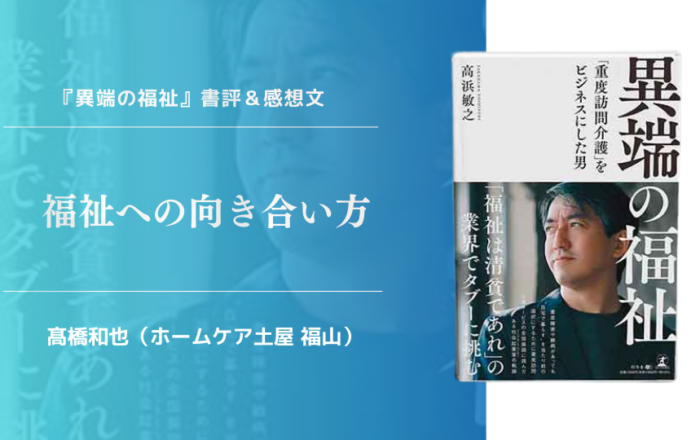





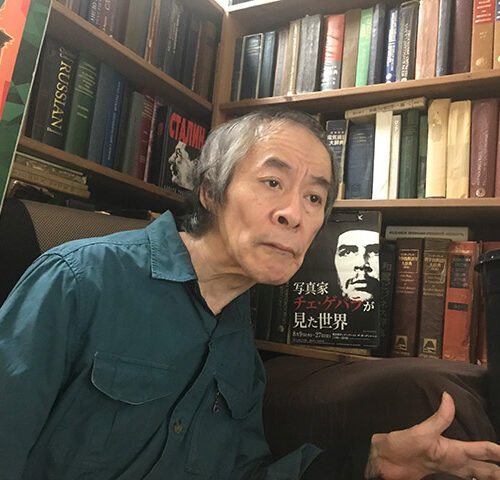

-1.png)















